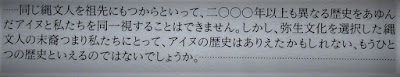「バリは、ほんとに金儲けの島になってしまった。地獄へ堕ちるよ」「慣習上の儀式や宗教儀礼は金で買えるようになってしまった」「浜辺の白い砂やそよ吹く風は、もう漁師のものじゃない。聞いたかい、バリの男は外国女の奴隷になって満足しているって」
バリ島出身のジャーナリスト、プトゥ・スティアの著作「Menggugat Bali」を翻訳した「バリ案内」(木犀社)の中で、スティアが友人の言葉として引用しているくだりだ。
だが、世界中から観光客がやってくる現在のバリのことではない。 今から30年以上前、この本が書かれた1986年のことだ。
1986年といえば、G5(先進5か国)による為替安定化のためのプラザ合意の翌年、急激な円高で多数の日本企業が東南アジアへ脱出していたころだ。 このころから東南アジアは確かに変わり始めた。 経済発展と外国人観光客の増加。 伝統社会の変化も始まった。
そのころのバリを知っている。 スティアの友人が言うほどバリ社会が変化していたとは思わなかった。 日本の農村を思わせる水田の風景、どこからか聞こえてくるガムランの音色、人々のほほえみ、そういったものが一緒になって独特のたおやかな雰囲気を醸し出していた。 だが、もちろん、そのころでも観光化の俗っぽさを感じることはできた。 われわれ外国人には、当時、それはまだたいしたことはない程度のものだったが、バリ人には既に破滅的な堕落になっていたのだろう。
11月に、バリの伝統を色濃く残しているとされる内陸部ウブドに、15年ぶりに行った。 この土地の田舎っぽさ、何もしないでぼんやりしていても退屈しない時間の流れ、ずっと昼寝をしていたい気持ちになれるのが好きで、いつかは住んでみたいな、と思っていたからだ。
だが、クルマでウブドに着いて、運転手から「ここだ」と言われても、そこがウブドだとわからなかった。 通りの両側は、ホテル、レストラン、バー、スパ、エステ、土産物屋、コンビニなどが、ぎっしりと並んでいた。 都会の繁華街のような光景。
15年前もこういった店はあった。 だが数ははるかに少なくて、建物と建物のあいだからは裏手に広がる水田を見渡すことができた。 あの田舎町は消えていた。 東京から7時間も飛行機に乗らなくても、こんな歓楽街なら電車ですぐのところにいくらでもある。
どうやら、スティアの友人が30年前に指摘したことをやっと感じることができたようだ。 冷静になってみれば、自分があまりにナイーブになっていたことはわかる。 東南アジアはどの国も30年のあいだに大変貌を遂げた。 バリだけが例外であるはずはない。 それでも嬉しかったのは、バリの人々の昔と変わらない優しい微笑みだった。
昔は、泥棒だの売春婦みたいな邪悪な人間は、ジャワ島などからやって来たよそ者で、バリの人間は悪いことはやらないと自慢していた。 多少の誇張ではあったろう。 ウブドの若者に、今はどうなんだ、と訊いてみた。 ニヤッと笑って、「今は、バリの人間でも悪いのが少しはいるよ」と言った。 きっと、”少し”ではなくて、”たくさん”いるのだろう。 そういう顔をしていた。